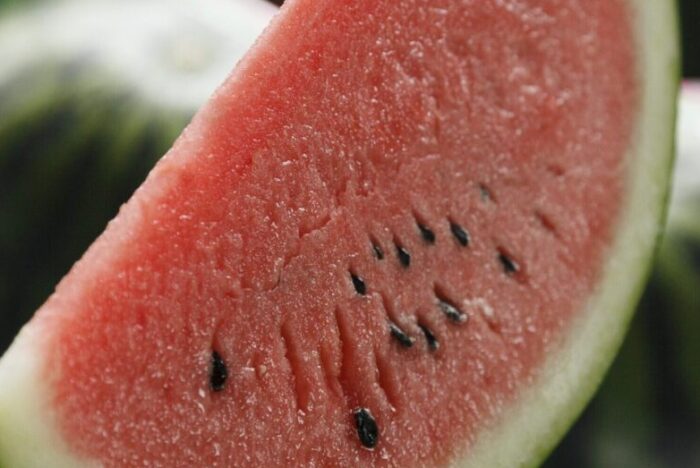【ようこそ発酵蔵へ・海外編】スペインの水稲栽培から始まる「地中海スタイルの新しい米の酒」
2025.09.04

text by Noriko Horikoshi / photographs by Shin Yamazawa
連載:ようこそ発酵蔵へ
酒、味噌、醤油、納豆といった日本の伝統発酵食品が、日本食ブームを背景に、海外で独自の発展を見せています。環境再生型農業の先進地であるスペイン有数の米どころで、SAKEを造り、麹造りの技術を生かした発酵調味料を商品化し、国内外から多くのファンを集めるスペイン・カタルーニャの蔵を訪ねます。
目次
- ■スペイン有数の米どころに誕生した酒蔵第一号
- ■この米には心白がある!大粒の在来品種で閃いた酒造り
- ■地中海の風土を映す柑橘の果実感が持ち味
- ■生物多様性を維持する循環型農法による米づくり
- ■免疫力を高める食材として“MISO”も主力商品に
スペイン有数の米どころに誕生した酒蔵第一号
バルセロナから地中海に沿って南へ約150km。カタルーニャ州最南部、エブロ川が地中海に流れ込む河口を囲んで広がる三角州“デルタ・デル・エブロ”は、南フランスのローヌデルタと並ぶヨーロッパ最大規模の湿原地帯として知られる。
その玄関口に位置するのが、人口4000人足らずの小さな町“ランポージャ”(L’ampolla)。クルーザーやヨットが停泊する港を見晴らす丘の中腹に、「KENSHO」という名の酒蔵がある。創業者のウンベルト・コンティ氏と妻のメリチェル・ジャルディさん夫妻(以下、敬称略)が、スペイン第1号のマイクロSAKEブリュワリーをこの地に構えたのは2015年春。近年、開業が相次ぐEU圏内のSAKE蔵の中でも、堂々の古参に数えられる一軒である。

蔵元杜氏であるウンベルトは、バルセロナの出身。大学では環境科学を専攻し、卒業後はニューヨークやバルセロナの企業で環境エンジニアとして活躍したが、デルタ・デル・エブロの水資源保全プロジェクトで後の伴侶となるメリチェルと出会い、運命が大きく変わる。ランポージャで4代続く農家に生まれたメリチェルは、農業シンクタンクで稲作専門の技術研究員を務める“米のプロ”でもあった。

デルタ・デル・エブロは年間14万トンもの生産量を誇るスペイン屈指の稲作地帯であり、早くからユネスコの生物圏保存地域に指定された経緯から、自然との共生が図られてきた環境再生型農業の先進地でもある。
「彼女とファミリーを通して、この一帯で栽培される食米、特に“ボンバ”と呼ばれる丸粒のジャポニカ米についての理解が深まり、そのエコロジカルな取り組みとクオリティに圧倒されました」とウンベルト。
とりわけ彼の心を捉えたのが、ボンバの中でも最高品質を誇る銘柄米“マリスマ”である。日本人にもおなじみのパエリャや、アロス・メロッソなどの米料理に使われる大粒米。風味の良さに定評があり、取引価格も高い。しかし、ニューヨーク勤務時代から和食や日本酒に親しみ、その味わいに魅了されてきたウンベルトが着目した点が、もうひとつ別にあった。
この米には心白がある!大粒の在来品種で閃いた酒造り

「粒の大きさだけでなく、心白があることです。しかも、白い部分は日本の酒米と同じ目の粗いでんぷん質が主成分。もしかしたら、このお米を使ってスペインローカルのSAKEが造れるのではないかと閃きました。また、デルタ沿岸のラグーンは淡水と海水が交じり合う汽水域で、日本酒と相性のよい牡蠣やムール貝、ウナギなど良質な海産物の宝庫でもあります。この共通性は、単なる偶然なんかじゃない。地元の誇りである素晴らしい米と、日本の伝統的な酒造りを組み合わせることで、“地中海スタイルの米の酒”という新しいジャンルを提案できるかもしれない、と。想像するだけで心が躍りました」
着想から事業化までの準備期間は、たっぷり7年。その間、日本各地の酒蔵を巡りながら醸造設備や技術の実際を学ぶ一方、自宅のガレージでデルタ・デル・エブロ産の米を一通り使った米麹や酒母の試作にも没頭。かねてから趣味でビールの自家醸造に勤しんでいたウンベルトのクラフトマンシップが、酒造りでもいかんなく発揮された格好だ。そして、気になる“マリスマ”の醸造適性はといえば――。
「パーフェクトでした。“バイア”や“セニア”といった他の代表的なジャポニカ米品種と比べて吸水性がよく、糖化力が旺盛。発酵の経過や香味も抜群で、山田錦や雄町と比べてどうかはわからないけれど(笑)、原料米として十分なポテンシャルをもつことが確信できました」



酒造米としての品質は精米技術にも大きく左右されるが、ここは米のエキスパートのメリチェルの出番だ。デルタ・デル・エブロには協同組合が運営する精米所があるものの、日本の醸造用精米機のような精度の高い設備がないため、心白を効率的に残す指示を細かく出しながら、60%と70%の2通りに精米をしてもらっているという。
「たくさん削っても米が割れにくく、蒸したときの弾力もしっかりしているのがマリスマの特徴。雑味の原因になる脂質やたんぱく質が、他のジャポニカ米より低いとする研究データもあります。つまり、良質な麹造りに向く条件が揃っているということ」と、彼女もプロ目線での太鼓判を押す。
地中海の風土を映す柑橘の果実感が持ち味
現在もマリスマ100%で造られる「KENSHOのSAKE」は、創設以来の定番である“にごり”と純米酒を含む全5種類。ワイン文化が根付く地中海の風土や嗜好性に添うよう、「旧知のワインと近いドリンカビリティーを意識」したアルコール度数12%前後の、いわゆる“低アル”に徹したラインナップだ。
年間を通して蔵内の温度を空調で一定に保ち、低温長時間発酵の吟醸造りを基本としているのも、ワインライクなすっきりした飲み口に近づけるため。清酒酵母は901号をメインに使用。一般にはリンゴのような上品な吟醸香を特徴とする酵母だが、「KENSHO」の酒造りでは「柑橘やパッションフルーツに近い酸のニュアンスが出て驚いた」と話す。


「蔵を立ち上げた10年前に比べ、SAKEを積極的に楽しもうとする人は確実に増えていますが、まだ“強くてキツい蒸留酒”と混同されることも少なくありません。まず、親しみを持って飲んでもらう意味でも、ワインと通じる柑橘の風味は好ましい特徴と捉えています」
そう表現される「KENSHO」の味わいには、確かにオレンジの爽やかな柑橘香と果皮を思わせるオイリーなほろ苦み、きゅっと締まったクエン酸系の甘酸っぱさが入り混じる。前々から「日本酒にはその土地名産の果物の特徴が反映される」と勝手に感じていたのだが、バレンシアに近い異国の酒蔵で、その実感はいよいよ深まった。地酒とは不思議なものだな、と思わずにいられない。
生物多様性を維持する循環型農法による米づくり
「KENSHO」の酒造りに使われるマリスマの圃場は、蔵から5㎞ほど離れた湿原の一角に広がる。デルタ・デル・エブロの稲作の歴史は比較的新しく、土地の産業として定着したのはエブロ運河が開通した19世紀後半以降のこと。20世紀に入って生態学的価値の高いデルタ地帯の自然環境が広く認知されるようになり、米づくりにおいては、生物多様性維持の観点から冬期灌水田での稲作が一般的な農法となってきた。秋の収穫が終わった水田に水を張ることで稲の刈り株から有機物が分解され、微生物の繁殖で土壌が肥え、さらにはラグーンに飛来する野生の水鳥が害虫となる水中生物を餌にするため、農薬を使わずに米づくりができる循環型農法である。

ウンベルトとメリチェル夫妻も、同じ方法で数年前から自社田での栽培をスタート。田植えは日本と同様に6月に行うが、醸造のルーティンに追われる彼らは、省力化のための新しい栽培法として機械を使った直播きも取り入れている。
「直播きは苗が育ちきらないうちに倒れやすいデメリットがあるのですが、この一帯ではコンパニオンプランツとして、水田の周りにオレンジやブドウやオリーブの木を植えるのが伝統になっていて、これらの植物が風除けになって稲の倒伏を防いでくれるのです」とメリチェル。一面に広がる水田では、山田錦を祖先にもつという新しい酒米“ユーロ2号”の実験栽培にも取り組んでいるという。

免疫力を高める食材として“MISO”も主力商品に
一方、酒造りを通して“麹”のパワーと可能性に魅せられた彼らの蔵では、2017年から自家製麹とデルタの塩田の海塩をベースに仕込む発酵食品づくりもスタート。醤油、味噌、味醂、塩麹、米酢などの発酵調味料に加え、甘酒、梅に似たスペイン産プラムの“シルエラ”を使った梅干し、まさかの納豆(!)まで、アイテムの幅広さは驚くばかり。
特に、日本酒と並ぶ主力商品に育ちつつある味噌は、白、赤の2種類の米味噌、麦味噌、豆味噌に加え、スペインのソウルフードともいえるガルバンソ(ひよこ豆)を使った味噌の仕込みも。麹菌由来の酵素を失活させないために、すべて非加熱の生味噌を製品化している。


もともとカタルーニャは自然派ワインや自然食品への傾倒が深い地域だが、「特にパンディミアを機に家庭の食生活への関心が高まり、免疫力を高める食材として“MISO”を求める人が一気に増えた」と二人は口を揃える。
現在は、地元住民や酒蔵ツアーの見学者を対象に、自社の発酵食品と地元産の食材を組み合わせた料理のワークショップを週末ごとに開催。これがまた、予約が瞬時に埋まってしまう人気ぶりというから頼もしい。プログラムには、当然ながら自慢のSAKEとのペアリング体験も含まれる。


「たとえば、熟成が進んでいない淡色の白味噌を夏野菜のサラダのドレッシングやガスパチョの塩味に使い、スパークリングSAKEと合わせたり。冬はグリルした魚や根菜に、濃色の赤味噌とアリオリソースのこっくりしたディップを添えて、にごりSAKEと一緒に。珍しさや一瞬の感動だけでなく、継続的に使いたくなる食材として意識してもらうために、実際の活用術や楽しみ方をきちんと伝えることが大切。そのためのアイデアは、途切れることなく湧いてきます。これも麹の力かもしれませんね(笑)」